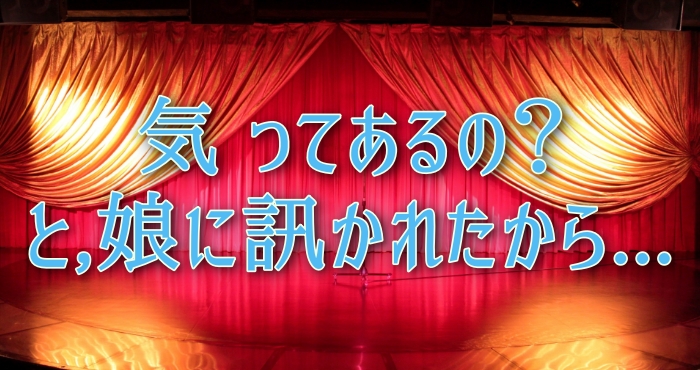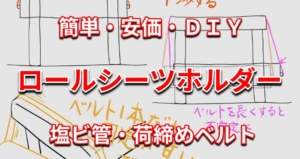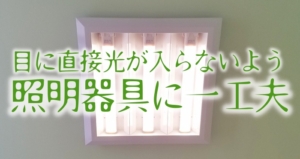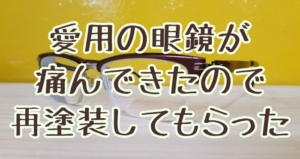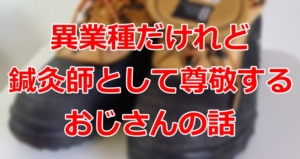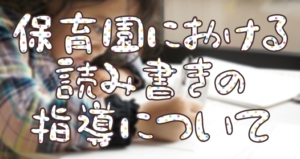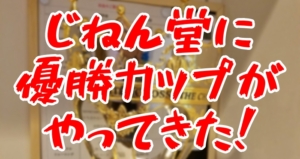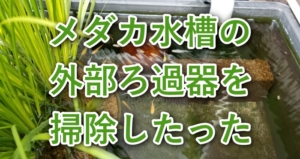一口に鍼灸と申しましても、実に様々な手法があります。
ざっくりと、「東洋医学の考え方で施術する鍼」と「現代医学的な考え方で施術する鍼」に分けて論じられることが多い印象です。そして、後者の手法と切っても切れないのが、“気” の概念。
この概念のおかげで施術が成り立っていると言えますし、この概念のせいで胡散臭いと思われてしまう側面もあります。
私はいわゆる折衷派で、東洋医学的な考えで施術する鍼の方に重きを置いています。そして折衷派でありながら、しばらくの間、国内にいくつかある団体のうちの一つで県支部長を務めていました。
今回は、そんな支部長時代の2014年。“気” ありきですべての話が進む団体の中にあって、“気”を「ないもの」と捉えていた私が行った問題提起を紹介します。
※文中の「“気”を扱う鍼」は、主に経絡治療と呼ばれる手法のことを指しています。
“気”って、あるの?

なあパパ。
はりきゅうのことで聞きたいことがあるんやけど。



お。何や?



“気”って本当にあるん?



分からんなあ。今のところ、あるか無いかで言えば「医学的には無い」としか言えやんわ。



分からんのに無いってどういうこと?



あのな。今の世の中において “ある” か “ない” かを判定するのは、いわゆる科学的な手法によっておこなわれるんさ。



かがくてきなしゅほう……。



うん。
何かの仕組みを知りたいと思ったら、「こうかもしれない」という仮説を立てて実験や測定をおこなって、その結果と “知ろうとしている仕組み” を矛盾なく結び付けて説明できやんとアカンのさ。
何らかのセンサーで捉えられたり数値で判定できたりすることを説明とするなら、今のところ、“気” の存在は説明のできていない仮説でしかないんよ。



なんかややこしいけど、説明が出来ないから「 “気” は無い」ってことなん?



それもちょっと違ってな。あることが説明できないのは、「あるかもしれないけど、無いかもしれない」っていうことなんさ。科学的にはな。



じゃあ、あるかもしれやんのや!
“気”はあるかもしれないけれど…



そう。あるかもしれやん。
せやけどな、考えてみな?
病院で、「あなたの身体に癌が見つかりました。当病院での治療は薬の点滴です。因みにこの薬は、今のところ癌に有効だという研究結果が一つも出ていません。どうしますか?」って聞かれたらどうよ。



そんな薬、ありえやんわ。癌に効かんってことやろ?



いや、有効だという研究結果が出ていないだけで、ひょっとしたら有効かもしれんよ。勧めてくるってことは、そこの病院では過去に何人かがその薬で寛解したんちゃう?
薬を使うタイミングとか、量とか、他の薬との組み合わせとか、あるいは特定の遺伝子をもつ人とか。条件によってはものすごく効くんやけど、研究ではそういう調べ方をしやんかったから、有効って結果に繋がらんかっただけかもよ?



それでも嫌やわ~。怪しすぎるやん。



そう思って当然やな。
人の身体を預かる現場において、科学的には(効果が)あるかもしやんし無いかもしれやんっていうのは、無いんと同じっちゅうことさ。
“気” もそう。医学的には無いんや。



うーん。その理屈やと、一般的にも無い気がするけど……。



あー。それやとパパは無いものを扱って商売をしとるってことになるなあ。詐欺師か呪い師みたいなもんってことかあ。



えー、そこまで言ってないけど……。



いやいや、ええんやで。
“気” はな、医学的には無いけど、科学的にはあるかもしれやんし無いかもしれやんもんなん。一般的にも無いと言いたくなるけれど、そういうもんなんさ。
あるような無いような医学と、ちゃんとある医学



なんかモヤモヤするわ。
パパのやっとることって、医学ちゃうの?



まあ、東洋医学なんて名前はついとるけど、いわゆる病院で保険適用になるような “標準治療” とは違うもんやな。



ひょうじゅんちりょう?



科学的な手法によって、現時点で一番有効であると認められた治療のことやな。ちゃんと “ある” 医療の代表みたいなもん。
その効果は100パーセントではないかもしれやんのやけどな。



100パーセント治らんくても、 “効果がある” って言えるん?



それはそうよ。ほかの方法よりも効くことと、どういう理屈で効くのか説明できることが大事やからな。
だからこそ、 “気” を扱う種類の鍼灸は標準治療にはなり得やんのよ。



そうか。“気”が「ないもの」やから。



そう!
ないものを使ってどうやって効果を説明するんやって話。
病院でも鍼をするところがあるよね?



でも、パパは若いころに病院で鍼をしとったやろ?



しとったで。
でも、パパが若いころに病院でしとった鍼に “気” は関係ないに?
反射を利用して筋肉を緩めたり、鍼の鈍い痛みで元の痛みを感じにくくしたりする方法やったんさ。
運動連鎖といって、身体のどこかが動くと連動して別の場所も動く法則みたいなもんがあるんやけど、それを利用して鍼をすることも多かったな。あとは神経の近くに鍼をして、その神経と関係のある部分に影響を与えようとすることもあった。
患者さんの身体に何が起こっているのかを、しっかり目で見て、触って、検査して、しかるべきポイントに鍼をするって感じ。
それでも健康保険は使えやんかったよ。つまり標準治療やないってことさ。



標準治療と違うってことは、パパが若いころにやっていた鍼は効かんってことなん?



いや、それもまた違うなあ。標準治療と違ったら効かんのかっていうと、そんなこともないんやで?
そのころパパがやっていた鍼は科学的な手法による実験や測定が行われているものもあったし、そのぶん医学的には “気” を扱う鍼よりも効果があると言えるんちゃう?
ただ、質の高い鍼の論文の数が標準治療に比べて圧倒的に少ないから、どうしても信用度が低くなってしまうんよ。



“気” を扱わんでもアカンのや……。



実際、パパの雇い主だったお医者さんは、「鍼はサービスでしかない」って、言うとったよ。時間をかけて施術したら嫌な顔をされたし、そのお医者さんが患者さんにする説明も、治療の選択肢がよその病院より多いことをアピールしたいがためのものって印象やったな。鍼はあくまでパフォーマンス。鍼師は猿回しのサルみたいなもんってとこさ。
それもこれも、医学的な信頼度の低さが原因なんな。これが “気” を扱う鍼やったら、さらに輪をかけてってことになるわさ。
“気”を扱う鍼も標準治療になり得るの?



じゃあ逆に、“気” を扱う鍼をしている人がもっと頑張って研究をしたら、標準治療として認められるかもしれやんってことやんな?



確かにそうかもしれんな。せやけど、それはものすごく難しい事やわ。



なんで?



それはな、“気”の存在どころか、パパがやっとる鍼の考え方や方法すべてが仮説やからなん。



ええー!?



大前提の “気” が仮説やのに、それを基にして考えられたものがすべて矛盾なく説明できるだなんて、そんなでたらめな話は無いやん?
実は、大昔の人が自然の仕組みを理解するために、「 “気” があったとしたら便利かも!」って仮説をたてて、それを証明せずに、さらに仮説を重ねて人の身体の働きにも当てはめて作ったのがパパのやっとる鍼なんさ。
陰陽五行説、臓腑説、気血津液学説、な!



あ、本当。“説” って。



せやからパパの脳味噌では、それぞれの仮説を証明するために科学的な手法を用いようにも、どこからどう手をつけたら良いのか分かりませ~ん。



アカンわ。
パパのお店で鍼をして「楽になった」って言ってくれとる人らが可哀想。



そんなこと言われても困るやん。楽になるのは事実やし、その楽にしている鍼は「“気” がある」ことによって成り立っとる方法なんやから。
仮説が仮説のままで矛盾もある理論には違いないけど、長年の経験によって編み出されたものは尊重しやなアカンで?



でも “無い” んやろ?



まあ、なぁ……。
一応、方法はある



ただ、“あるかもしれない”の割合を増やすことは、できなくもないんやで?
ひとつひとつの仮説を科学的手法で説明していくことはめっちゃ難しいし、標準治療にはなるべくもない(なる必要もないと思う)けど、「医学的根拠には乏しいが、“気” を扱う鍼にも一定の効果はあるようだ」みたいな認識を持ってもらうことはできるかもしれやんのさ。うまくいけば、「“気”はあると考えることが合理的だ」ってなるかもしれん。



どうやって?



「“気” を扱う鍼をしたら、体やこころがこのように変化しました」っていう数値的なデータをものすごくたくさん集めて発表し続ければエエんよ。ちゃんとした手順を踏んで、しかるべき場所でな。



100人とか?



いやいや、全然。
それこそ10万人くらい。
“気” を扱わない鍼をした場合と比較したり、10年くらいの経過を観察したりするのもエエかもしれん。
ちなみにパパは「“気” を扱う鍼をすると、筋肉がどれくらい柔らかくなるか」というテーマで、鍼の前と後とで筋肉の硬さを測ったことがあるんやに?
ツボにちゃんと鍼をした場合と、ツボでないところに鍼をした場合とで比較したんさ。



へぇ~。



一応、ツボに鍼をした方が筋肉を柔らかくすることができたわ。それで、みんなの前で発表もした。
せやけど、その検証で鍼をした人数はたったの20人で、しかもパパの調べた限りでは同じような発表をしている人が日本には1人もおらんかったんさ。
それがまだ5年前(2015年当時)やに?



それやと10万人って、気の遠くなるような話やな。



確かに気の遠くなるような話やな。せやけど、大昔の中国で “気” の考えを基に鍼をする方法が出来上がるまでには、こういう観察が何百年もかけて行われとったんやと思うよ。それこそ代々受け継がれながら。
せやから、やってできないことは無いはずなんやけどな。
まあ、パパのやっとる “気” を扱う鍼は大昔の方法を昭和の時代になってからアレンジしたものやし、だからってわけでは無いかもしれんのやけど、一つ大きな問題もあるんさ。
大きな問題



なに?
大きな問題って。



科学的手法の説明のところで話し忘れてとったんやけど、“気”を扱う鍼は再現性に乏しいんよ。



さいげんせい?



「誰がやっても同じ結果が出せるか」ってことやな(実際はちょっと違うけど……)。割烹着の研究員にしか作れないSTAP細胞では困るのと同じよ。データの信憑性にかかわってくるから。でもそれがなかなか出せやんのやわ。



方法が同じやのに、なんでなん?



仮説が仮説のままやからやな。
一つの現象に対して色んな答えが出せてしまえるんよ。特に、いくつかの症状を持っている患者さんの治療をする場合に、より顕著になるん。



どの症状を最初に治すかってこと?



いいや。
“気” を扱う鍼では、患者さんの身体の状態を、病名の代わりに「証(あかし)」という尺度で表現するんさ。
症状を見たり聴いたり身体の色んな部分を触ったりして証を決めて、それに応じた鍼をするん。その証はどんなに症状が多くても1回の施術でひとつしか付かんの。(あくまでも経絡治療の場合)



うん。



せやけどその証を決める時、見たり聴いたり触ったりして分かったことの解釈や理解によっては、施術者それぞれで全然違う証になってしまう時があるんさ。
それに、証を立てて治療をしてみて、それが間違いだった時も、後付けの解釈でいくらでも証を変更してやり直しができてしまうんよ。



「1回の治療でひとつ」とか言いながら、全然ひとつちゃうんや。それ知っとるわ。ファジーっていうんやろ?



おー、結構昔に流行った言葉を知っとるな。パパの高校の物理の先生のあだ名が “ファジー” やったわ。
まあ、それはさておき。見たり聴いたりした症状の解釈が色々になってしまうのは、元の理論が仮説のままで矛盾だらけやからしゃあない(いや、しゃあないままで終わらしたらアカン問題ではある)んやけど、“触って分かること”ですら施術者によって理解違ってきてしまうのは、ほんまに大問題なんさな。



うん?



解釈もへったくれもなくなるんさ。まさに今そこにあって触れることのできるものですら、一つの答えにまとまらんってことよ。
これはもう、再現性なんて言葉を出すのが憚られるくらいの大問題やで?



でも、なんでそうなるん?
触り方が下手なん?



下手って言うてしもたらそれで終わりなんやけどな。触ることで診ようとしているものは同じはずやのに、実際に診えているものが施術者のレベルによって違ってくるからなんさ。



同じ場所を触っても?



そう。
同じ場所を、一見同じように触っていても。



不思議やな。



不思議やろ?
これが診るべき場所の “気” を診て捉えているか捉えていないかの違いなんちゃうかなって、パパは思うんさ。
“気” を扱う鍼灸をしとんのに、診るべき場所の “気” をちゃんと診ることができやんかったら、そこから鍼をした時に「ちゃんと診られている人」との差が一段と大きくなりそうちゃう?



うん。全然別なものになりそう……っていうか、そうなったらアカンやん。



まあ、そもそも「ないもの」を触ろうとしとるんやしな。
ありもしないものを触った気になっとるだけかもしれんという疑念が、パパの中には常にあるんやに?
それでも前に進むのです!



そうは言っても、この「触って分かること問題」をクリアできれば、かなり前進できると思うんさな。再現性を得るための前提条件を揃えるって感じやな。
パパがしとる鍼は、同じ “気” を扱う鍼のなかでも “症状の解釈” の部分を控えめにして、なるべく触って分かったことから “証” を決めるようにしとる流派なんさ。
やろうとしていることはすごくシンプル。
パパはどちらかというと理屈っぽいタイプやから、最初はそのことが腑に落ちんかったんやけど、最近はこの方が証の間違えが少ないのかもと思い始めてとるんさ。症状の解釈をこねくり回さんでエエもんな。



うーん、そういうことなんかなぁ



そうやで?
だからパパはなるべく、患者さんの身体の表面に表れている変化を診逃さんように気を付けとんの。
色んなところを触って悪いところ、いや、悪いところとちゃうな、他と違うところを見つけるって感じやな。“気”が「ないもの」だったとしても、体表面の微細な変化は確かにそこにあって、これを昔の人は“気”の変化の現れだと捉えとったんやろなって。
でもこれがなかなか難しいんよ。“Don’t think, feel.” ブルース・リーやな。



ふーん(ブルース・リーは知らんけど…)。
なんか、病院でしとった鍼と似とるんちゃう?



そうかなあ。診ようとしとるものはずいぶん違うけど……。現象を観察するとか、変に理屈をつけて解釈しやんのは似とるかもな。
結局は若いころから慣れ親しんだ方法がしっくりくるってことか。こりゃエエわ。



パパ、楽しそうやな。



まあな。自分にしっくりくるやり方で、間違いが少なくなって、しかも患者さんに喜んでもらえるなら、これはもう楽しいと言えるな。
ただそれはパパ個人のレベルでの話で、さっきも言うた再現性を高めるためには、みんなが同じ診かたで同じ場所にある同じものを捉えられやなアカンから、「有るかもしれないけど、無いかもしれない」ものを扱っている時点でものすごくハードルが高いし、現状を見渡す限りではとても実現できるとは思えやんけど、せめて同じ流派の中でだけでも再現性を高める(たくさんの検証を世に出す)ことが出来るように、パパも何かしらの働きができればエエなと考えとるよ。



そうなんや。がんばってな。



うん。ぼちぼちいくわ。
こういう会話を、娘としたい。
今回の文章は、当時所属していた団体(流派)の機関紙に「父と娘の妄想劇場」として寄稿したものです。2015年の新年号に掲載してもらおうと書いたので、“割烹着の研究員”なんて時事ネタが入っています。実際に掲載された文章は標準語の会話で、文字数もいくらか削っていたと記憶しています。
その後、流派内での働きかけは失敗に終わり、現在は個人で臨床研究を行っています。また、2020年7月現在、娘とこのような話は出来ていません。できる見込みもありません。
現実はなかなか厳しいものです。
さて、余談ではありますが、標準治療が云々なんてことを書くと、「鍼の腕に自信がないから医者(科学的手法・現代医学的な知識)に迎合するのだ」といった批判をする者が必ず出てきます。
「古代中国で東洋医学が成立した段階で仮説の証明は終了している。だから今さら科学的手法なんて必要ない!」などといったものもあるでしょう。
両者の気持ちは分からなくもないですし、「西洋医学的鍼灸!現代鍼灸!エビデンス!」と、EBMの意味も分からずに喚く連中にも辟易していますが、いささか的外れではないかと思います。
鍼灸師は鍼灸師、医師は医師。それぞれの得意なことをすれば良いだけです。
ただし、常に自分の施術が病体にどのような影響を及ぼすかを観察し考察することは欠かしてはなりません。自信のあるなしに関わらず、検証し続けることで、技術や理論への理解が進むのです。盲目的に伝統的な手法を病体に当てはめて行使するだけでは先が知れています。古典鍼灸の技術の全てが現代に伝わっているわけでは無いですから。
これは迎合でも証明でもありません。
研鑽なのです。
そして、観察や考察をする際の方法として、いわゆる科学的手法を用いることが理にかなっているのではないかと思うのです。単純に、便利で信頼性が高いからです。鍼灸師以外の医療関係者にも検証過程や結果が理解できるのは副次的なものというわけです。
付け加えるならば、鍼灸では手に負えない病症を鑑別するためにも、現代医学的な知識は役立ちます。
これらの行為や知識を必要ないと強弁できる鍼灸師は、自分に能力がないことを認めたくなくて意固地になっているか、神がかり的な達人かのどちらかだろうと、私は感じています。