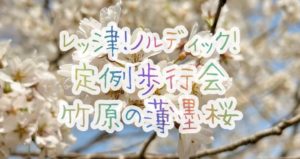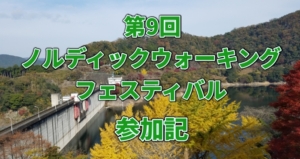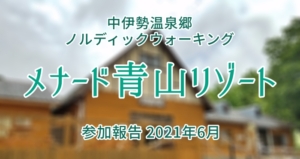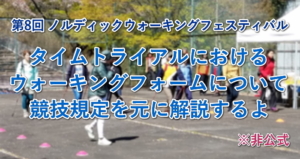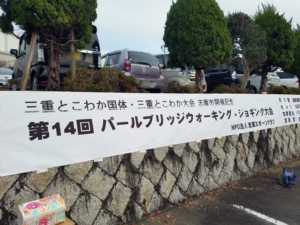前回のエントリーでは熟練者でも路面の影響で消費エネルギーに変化が起こりうることをお示ししました。
「それのどこが“騙されるな”なわけ?」
というご意見もあるかと存じますが、『ノルディックウォーキングは○○』と、十把一絡げに都合の良い効果だけを宣伝するのが気に食わない……というところを出発点に、頻出するキーワードである「消費エネルギー」に注目して様々な事例を紹介している中の一要素とご理解いただければ幸いです。
それから、前回は路面状況によってはポールが滑ってしまってしっかり押せない場合があると自分自身の経験を引き合いに出しながら書きましたが、ひょっとしたら、滑ってしまうのは私の技術の問題かもしれません。ですから若干記事の信憑性が低いのですが、まあ、気にせず進めていきますね。
フォームとパッドの話
さて、ノルディックポールの先端についているパッド。
形状から考えて、最大限にグリップを得るためにはポールを大体45度の角度で路面に押しつけ続ける必要があると考えられます。
最大限にグリップを得られれば、それだけポールを力強く押すことができ、上半身の力を路面へしっかり伝えることができます。歩行速度は速くなりますし、当然、消費エネルギーも高くなります。

ここで、ノルディックウォーキング中の腕の振りについてですが、教科書的には『自然に大きく、肘をあまり曲げずに』となっています。
しかし、肘をあまり曲げない状態で固定したままポールを45度で押し続けるのは非常に難しいのが現実です。路面に突いた時は45度であっても、腕(拳)が身体の側面に近づくにつれて45度よりも寝てくる(角度が浅くなってくる)のです。そしてポールが寝てくると、地面に対して垂直な力が小さくなって、真後ろに向かう力が大きくなるうえに、パッドの形状からも路面をとらえる面積が小さくなるので、滑りやすくなってしまいます。少なくとも私はそこでよく滑らせてしまいます。
推進力を得るだけなら45度よりも小さい角度で押した方が有利なはずなのに、いざそうすると滑ってしまって押せないわけです。
ではどうすれば良いかというと、ポールが安定してグリップする45度で路面を押し続けられるように、スウィングした腕が身体の側面に近づくにつれて肘を曲げていったり、身体の上下動で調節(これは自然に行われるはずです)したりするのです。

そして、身体の側面を通り過ぎたら再び肘を伸ばしていけば、ポールを押し切った最後の姿勢が教科書どおりにビシっと格好良くなります。(後述しますが、肘を伸ばすことで大きな推進力を得るわけではありません)
肘を曲げたままのフォーム
しかし、最後の段階で肘を伸ばさないフォームでウォーキングする者も一定の割合で存在します。身体の側面をとおりすぎる時に曲げた肘を、ポールを押し切るまでその角度でキープ……というフォーム。
このフォームでポールを後ろまで押すために、身体の後方で肩甲骨の挙上を伴って肘を高く上げていて、かなりダイナミックに腕を振っているように見えます。
個人的な感想としては、身体の側面を腕が通り過ぎた後は力が上に逃げがちで、フィニッシュで肘を伸ばすやり方に比べるとしっかりは押せてない気がします(そういう人が多いように感じます)。
もちろん、これはあくまで初心者とか、中級者レベルでの話です。
では高いレベルだとどうなのかというと、例えばノルディックスキー経験者のインストラクターは、肘を曲げつつも強く押せているそうです。
私がベーシックインストラクターの資格を取得する際に……
 じねん堂
じねん堂海外のナショナルコーチ1の中で、ポールを後ろへ押す際にフィニッシュで肘を曲げたままの者が見受けられるますけど、教科書には肘を伸ばすとなっていますよね。実際のところ、肘は伸ばすのか曲げるのか、どっちなんでしょう?
という質問を講師のナショナルコーチにぶつけたところ、
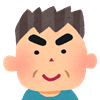
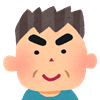
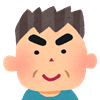
教科書的には伸ばすのが本当だけど、クロスカントリースキーの経験者たちは曲げてるね
との返答がありました。
スウィングの後半で肘を曲げていても、しっかりと押せてるならOKなのです。
肩甲骨の動き(挙上ではない)や体幹の回旋を使って、力強く押しているとのことでした。
ポールを使う目的は推進力を得るためですから、力強く押せればそれで良いのです。異論はありません。私も、腕のスウィングの最終局面における肘の完全進展は、あくまで背中の筋肉を使って行われてきたスウィングの延長上に生じているのであって、比較的ゆっくりなテンポで大きく歩くからこそ可能なものであり、肘を伸ばす力で大きな推進力を得ているわけではないと考えています。
たしかにクロスカントリースキーの競技では、長いストックを使っていて、肘も完全には伸ばしていません。しかしこれは、歩くのではなくて滑ることが大きな理由を占めていて、滑るために長く押すうえで、長いストックが必要なのと、肘を伸ばす上腕三頭筋が速筋繊維の割合の多い小さな筋肉なため、バンバン推進力を得るために使っていたらすぐに疲労で動かなくなってしまうので、そこを使わずに背中の筋肉の引く力で推進力を得ているのではないでしょうか。そしてそもそもテンポが速いので、肘を完全に伸ばす暇がない。伸ばすくらいなら次の押す動作に入りたい。そのように思えます。ノルディックウォーキングで肘を伸ばすかどうかとは別の問題な気もしますが、この辺は専門家に話を聞いた事が無いので、言及を避けたいです。
熟練者の省エネ運転
ちょっと長くなってきましたけれど、そろそろこのあたりで、今回(前回に引き続いて)述べたい部分に差し掛かってきます。
それは、熟練者が、一見すると同じようなフォームでノルディックウォーキングしても消費エネルギーが変化する要因について。
実はこの、肘を曲げて後ろへ高く挙げるするテクニック。別にポールを後ろまで押し続けなくても見た目を似せることが可能なのです。
先に述べた“力が逃げがち”どころか、力を全然入れなくても、できてしまうのです。
後ろへ押す距離や力を、肘や肩で緩衝しながら上へ逃がしているのですから、力を込めて押しているのは、せいぜい腕が身体の横を通る辺りまで。もしかしたら、そこの部分でさえ押していないかもしれません。
それでもダイナミックに歩いているように見えてしまう!
つまり、熟練者がダイナミックにノルディックウォーキングして、さぞ運動強度も高いんだろうと思ったら、実際は省エネ運転だったということもあり得るのです。上手いと見せかけるには最適なフォームかもしれません。
ポールで路面を突いたところから見ていると、身体の側面を過ぎた辺りから急にヒュッと肘を持ち上げるような、身体が前に進む速度と上肢帯の動く速度(あるいはポールが路面を捉えている間における上肢帯の動く速度)にアンバランスさの見られる歩き方だったら、おそらくそれです。
肘を曲げたまま高く上げるフォームの最後の部分でヒョイっと肘を伸ばす人も見かけます。
肘を最後まで伸ばしきるフォームでも省エネ運転は可能ということです。因みに、省エネ運転かどうかは歩行中のポールの角度で見分けます。肘をヒョイっと伸ばす局面でポールの角度が立ってきますから、一目瞭然です(理想的なフォームだと、後ろに伸ばした腕とポールとはほぼ一直線)。
経験者であれば、ポールを短めに設定することでこのような動作が容易に再現できます。お試しあれ。
省エネフォームがダメなわけではない
今回は省エネフォームを悪し様に言う(書く?)ような展開でしたが、そういうフォーム自体、ノルディックウォーキングに熟練してこないと出来ません。さらに、歩く距離や目的によって上肢帯(腕)への力の込め方は違ってきて当たり前です。クロスカントリースキーの部分でも述べましたが、長い距離を歩くのにガンガン腕を使ったら、歩き切る前に腕が疲労で駄目になってしまいます。
加えて、団体によっても推奨するフォームが若干違います。
私はJNFA(とINWA)の所属ですから、主張も分析もそっち寄りになってきまが、他団体では腕を振るのではなくて肘を引くように指導する場合もあるようです。“スウィング”と“プル”の違いは意外に大きいのです。
ですから、正味な話、肘が曲がる曲がらない・最後まで押す押さないといった要素だけを切り取って責めるのはお門違いというものです。とはいえ、教科書的には最後に肘を伸ばすのが本来の正しいとされる(と教わった)フォームですし、ここまで消費エネルギーに拘って記事を書いてきていますので、敢えてお示しした次第です。
機会があったらインストラクターやデモンストレーターの腕の動きを注視してみてください。それはそれで面白いと思います。
- ノルディックウォーキングの国際団体であるINWA認定の上位資格。ベーシックインストラクターはINWA傘下の国内団体であるJNFA認定資格 ↩︎
※2012年9月公開の記事を加筆修正