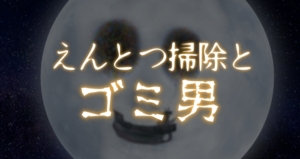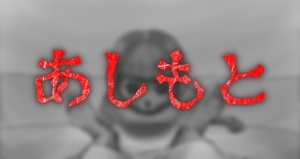今をさかのぼること20余年。私は京都の大学に通っていた。
京都と言っても、京都駅から山陰線で1時間半ほどかかる山間の町だ。間近に迫る山と生活道路の間を埋めるように田圃が広がり、初夏には小さな川で蛍が舞う。のどかな場所に私の通う大学はあった。
そのころ知り合った地元の女性にMさんがいた。バイト先の社員さんで、一つ年上。長身の姉御肌。暇な私と時々飲んだり遊んだりしてくれた。
彼女はいわゆる “見える家系” の人だ。子供のころからいくつもの不思議な出来事を体験してきたと言う。
今回は、そんなMさんから聞いた話を一つ紹介したいと思う。
Mさんがまだ小学校に上がる前くらいのころ、一人で祖父の家に遊びに行った。
農業を営む祖父の家の敷地は広く、大きな母屋、倉庫、離れと、小さな子供が遊ぶには十分だった。活発な少女だったMさんは、探検ごっこと称して母屋の床下に入って割れた湯飲みを見つけたり、倉庫の奥にしまわれている古めかしい道具をあちこち触ったりしていた。
そうこうしているうちに、Mさんは離れの前までやってきた。祖父からは入ってはならないと言われているが、それを守るMさんではなかった。
きっとこの部屋には祖父の宝物が置かれているに違いない。
少し重い引き戸を開けて離れの中に入ると、思った通り。6畳程度の部屋には所狭しと物が置かれていた。絵の描かれた皿、無数の木の箱、鎧兜、こけし等の人形…。まさに宝物庫だった。
胸を高鳴らせながらあちこち視線を移していると、ある物に目が留まった。床に置かれた胸ほどの高さの箱である。箱には布がかけられていて、中身が何かは分からない。布を取り去って中身を確認したいが、祖父の宝物に触ったことが知れると叱られるかもしれない。しかしなぜだか無性に気になる。
ついにMさんは誘惑に負け、箱を覆う布をどけた。
箱と思っていたものは、扉の付いたガラスケースだった。
中には可愛い人形がちょこんと座っていた。青いドレス、金色の巻き髪、ドレスと同じ青い瞳。右手には花束を持っている。いわゆるフランス人形だ。
Mさんはその人形と遊びたくなった。就学前の女の子なのだ。可愛い人形を前にしたら無理もない。ただ、ケースから出すのはさすがに気が引けたので、前に座って “おはなしごっこ” をすることにした。
「お名前は何ていうの?」
「どこからきたの?」
可愛い人形と仲良くなりたくて、話しかけた。
すると、徐に人形が右手をMさんの方へと差し出した。
「コレ、アゲル」
急に怖くなったMさんは、一目散に離れから逃げ出した。
しばらくして祖父が農作業から帰ってくると、Mさんは泣きながら事の顛末を話した。
「おまえ、そんなもん受け取ったら、入れ代わられるぞ!」
祖父の雷が落ちた。
離れは祖父の宝物庫などではなかった。
“見える家系” の一人である祖父は、その方面では一目置かれる存在で、遠くの町から困りごとの相談をしに来る者があったり、お祓いのようなことをする場合もあったりしたそうだ。また、持ち主の手に余る「曰く付きの品」を預かることも少なくなく、そういった預かり品を保管していたのが件の離れだったのだ。
「ずっと後になって知ったんやけどな」
Mさんは言った。
半分魅入られつつも難を逃れられたのは、やはりMさんが受け継いだ能力のおかげなのだろうと、あっけらかんとした口調で話す彼女の姿を見て思った。